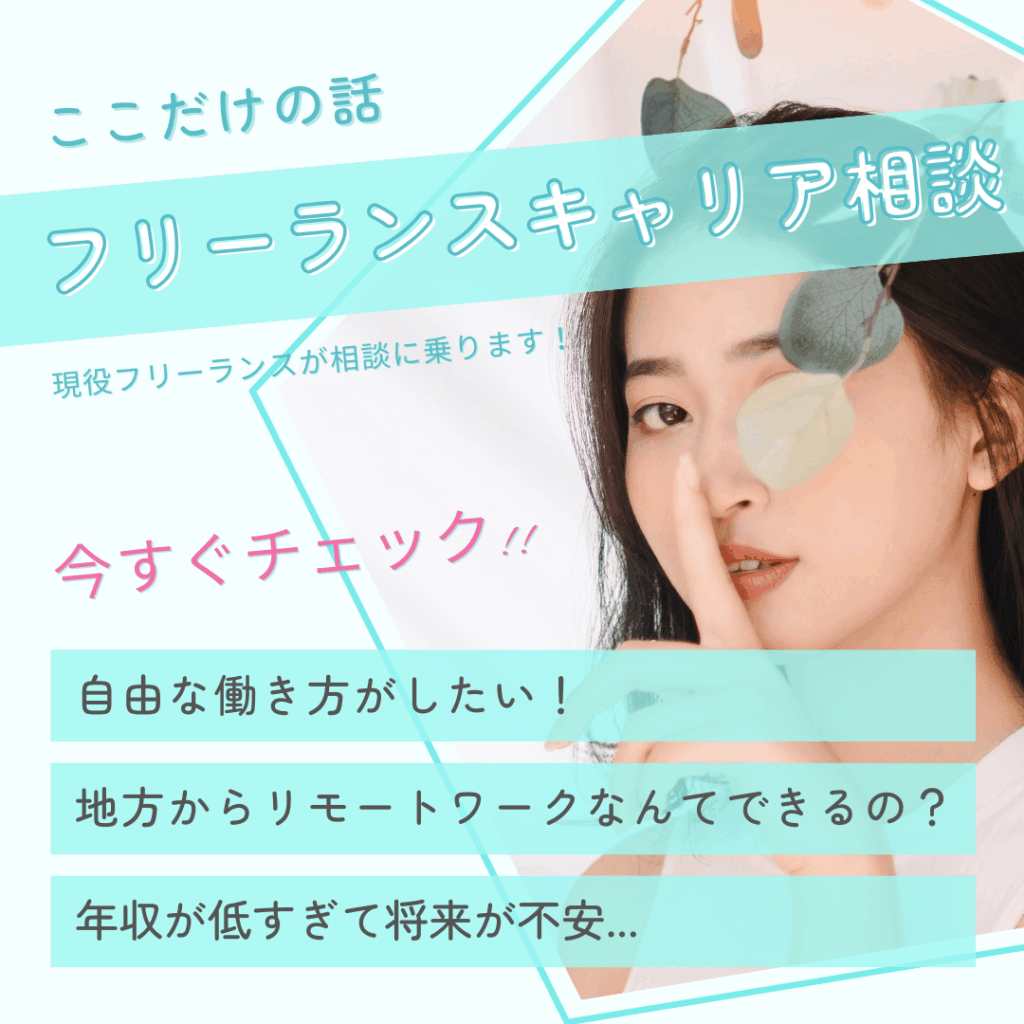夜勤のメリットは大きいけど、体力的に続けられるか不安…
そんな悩みを持っていませんか?今回の記事は、
✅「女性でもインフラエンジニアとして夜勤できるかな…」
✅「夜勤のメリットは大きいけど、体力的に続けられるか不安…」
✅「将来、結婚や出産を考えると夜勤での勤務は厳しそうだな…」
そんな悩みを抱える女性のあなたに、おすすめの記事です!
現在IT業界では人材不足が深刻化し、24時間365日システムの安定稼働を支えるインフラエンジニアの需要が高まっています。その中でも特に「夜勤」は、高い給与や柔軟な生活スタイルといったメリットがある一方で、体力面や健康面での懸念も。
「夜勤」という言葉を聞くと、多くの女性は「つらそう」「続けられるか不安」というイメージを持つかもしれません。私も約5年前、エンジニア職への転職を考えたとき、まさにそんな不安を抱えていました。
今回は、実際に夜勤を経験した周囲の女性インフラエンジニアの生の声と共に、夜勤の実態、キャリアパス、ライフステージに合わせた働き方まで徹底解説します。この記事を読めば、あなたが女性インフラエンジニアとして夜勤を選ぶべきかどうか、判断材料が手に入るはずです。

気になる箇所あったらコメントで教えてね。
なお、この記事は約3分で読める内容です。忙しいあなたのために、要点をまとめていますので、気になる部分から読み進めてくださいね!
なぜ 夜勤有りのインフラエンジニアが女性に注目されているのか
近年、テレワークの普及やワークライフバランスへの意識の高まりから、「働き方の多様性」が重視されるようになりました。特に女性エンジニアにとって、夜勤での勤務という選択肢が注目を集めている理由を見ていきましょう。
夜勤のメリット|収入アップ・時間の自由
まず最大のメリットは「収入アップ」です。インフラエンジニアの夜勤対応では、基本給に加えて25%〜50%程度の夜勤手当が付くことが一般的。私の知り合いのインフラエンジニア女性の場合、日勤時代と比較して年収が約120万円アップしました。
具体的な例を挙げると、月給30万円の場合、夜勤手当(30%)で9万円、合計39万円となり、年間では108万円のアップになります。さらに残業代なども含めると、日勤と比べて年収120〜150万円増加するケースも少なくありません。
また、平日日中に自由な時間が持てることも大きなメリットです。一例として、夜勤(23時〜翌8時)の翌日は休みなので、平日の昼間に銀行や病院、役所などの用事を済ませられるのが便利という話も。また、平日の空いている時間にジムやカフェに行けるのも嬉しいポイントです。
さらに、通勤時の混雑を避けられることもストレス軽減につながります。満員電車でギュウギュウ詰めになる必要がないため、通勤時のストレスが大幅に軽減され、精神的な余裕が生まれます。
ライフスタイルに合わせた働き方ができる
夜勤の大きな魅力は、ライフスタイルに合わせた時間の使い方ができることです。例えば、昼間の時間を使って副業やスキルアップに充てることができます。私の知り合い女性は夜勤の合間に、昼間は別のIT企業で副業エンジニアとして参画し、収入を大幅UPさせていました。
また、時間の融通が利く職場が多いのも特徴です。シフト制であることが多く、同僚との調整次第で休みを取りやすい環境があります。急な予定ができても、交代要員を見つけやすいという声もよく聞きます。
さらに、日勤よりも業務がルーティン化していることが多いため、業務の予測がしやすく、計画的に時間を使えるというメリットもあります。監視業務や定期的なチェック作業など、手順が確立されていることが多いため、未経験者でも比較的取り組みやすい場合があります。
夜勤ならではの大変さと課題
しかし、当然ながら夜勤には大変な面もあります。最も大きな課題は生活リズムの乱れです。人間の体は本来、夜に睡眠を取るように設計されているため、昼夜逆転の生活は体に大きな負担をかけます。
私の知り合いのインフラエンジニア女性の場合、夜勤を始めて最初の3ヶ月は常に疲労感があり、休日は寝てばかりいました。また、友人との予定が合わなくなり、社会生活に支障が出ることもあります。休日に友人と会う約束をしても、体のリズムが夜勤モードのままで朝早く起きられず、約束の時間に間に合わないこともありました。
さらに、夜間の孤独感や睡魔との戦いもつらい部分です。真夜中のオフィスは静まり返り、システムの警告音だけが鳴り響く中、眠気と戦いながら集中力を保つことは容易ではありません。夜中の2〜3時頃は特に眠気が襲ってくるため、強いコーヒーや軽い運動で対抗していたそうです。
夜勤の「きつさ」を女性目線で正直に語る
夜勤の実態について、周りの事例を含め、女性目線で率直にお伝えします。美化せず、リアルな側面をお話しすることで、これから夜勤を検討している方の参考になれば幸いです。
体調への影響と対策
夜勤最大の課題は、体調管理の難しさです。特に女性の場合、男性と比べて体力面で不利に感じることも少なくありません。
睡眠リズムの乱れは、単なる疲労感だけでなく、自律神経にも影響します。夜勤を始めてから不眠症になり、休日も十分な睡眠が取れないという悪循環に陥る例も。また、女性特有の問題として、生理周期の乱れを経験した方もいるようです。ホルモンバランスが崩れ、生理不順や肌荒れなどの症状も現れるとなると、なかなか続けるのは大変です。
これらの問題に対処するため、以下のような対策を取ることをおすすめします。
- 帰宅後すぐに就寝し、まとまった時間の睡眠を確保する
- 遮光カーテンや耳栓を使用して睡眠環境を整える
- マグネシウムやビタミンBなどのサプリメントで睡眠の質を高める
- 仮眠を効果的に取り入れる(20〜30分の短時間仮眠が効果的)
- 規則正しい食事で体内時計をサポートする
対策として、夜勤明けは必ず7時間以上の睡眠を確保し、遮光カーテンと耳栓を併用することで、少しずつ体が適応していきます。また、職場での仮眠も重要です。会社によっては「シエスタ制度」で2〜3時間程度の仮眠が認められていることもあるので、もし転職を考える時は、その点も確認しておくと安心です。
人間関係・孤独感の問題
夜勤の意外な苦労として、「人間関係の希薄化」があります。日勤帯と異なり、夜間はスタッフが少なく、場合によっては一人で勤務することもあります。そのため、職場での人間関係が構築しにくく、孤独感を感じることが多いです。
周囲のインフラエンジニアの事例です。夜勤は基本的に2名体制でしたが、相手が別フロアで作業していることも多く、実質的に一人で作業する時間がほとんどでした。また、日勤のチームメンバーとは顔を合わせる機会が少なく、情報共有やコミュニケーションの取り方に苦労した、とのこと。
これに対処するためには、
- チャットツール(SlackやTeamsなど)を活用して日勤メンバーとの連絡を密にする
- 定期的なオンラインミーティングに参加してコミュニケーションを深める
- 月に1〜2回は日勤帯の時間に出社し、チームメンバーと対面で会話する機会を作る
- 夜勤メンバー同士でのコミュニティを形成する
孤独感を解消するためには、意識的にコミュニケーションを取る努力が必要です。月に一度の全体ミーティングには必ず参加する、または週に一度はランチタイムに出社して同僚と交流するようにするなどルール化するのも良いでしょう。これにより、チームの一員としての所属感を維持することに繋がります。
家庭・育児・パートナーとの両立の難しさ
夜勤を続けていく上で最も大きな課題となるのが、家庭生活との両立です。特に結婚や出産後は、夜勤の継続が難しくなるケースが多いです。
家族と生活時間がずれることで、コミュニケーション不足や家事分担の偏りが生じやすくなります。私の先輩は、夜勤を続けながら結婚生活を送っていましたが、パートナーとの時間が取れずに関係が悪化してしまったというケースもありました。
また、子育てとの両立はさらに難しい課題です。保育園の送り迎えや子どもの急な発熱など、予期せぬ事態に対応するためには、パートナーや家族の強力なサポートが不可欠です。
実際に夜勤と育児を両立している女性エンジニアの例では、
- パートナーが柔軟な勤務体制で協力(在宅勤務や時短勤務など)
- 実家の親や親族の協力を得られる環境にある
- 夜間保育や24時間保育施設を利用している
- 週3日の夜勤に減らし、残りは在宅勤務にするなど柔軟な働き方を実現
夜勤と家庭の両立は決して不可能ではありませんが、周囲のサポート体制と職場の理解が必要不可欠です。キャリアプランを考える際には、家族の協力体制についても現実的に考慮する必要があります。
女性インフラエンジニアのライフステージ別働き方
女性のライフステージは変化に富んでいます。独身時代、結婚後、出産・育児期、そして子育てが一段落した後と、ライフステージごとに最適な働き方は変わってきます。それぞれのステージで夜勤をどう位置づけるかを考えていきましょう。
独身時代に夜勤でキャリアを積む
20代〜30代前半の独身時代は、夜勤を通じてキャリアとスキルを集中的に積むのに適した時期です。この時期は体力も充実しており、夜勤の負担も比較的受け入れやすい時期といえます。
ある女性インフラエンジニアのケースでは、未経験からインフラエンジニアに転職した際、あえて夜勤を選んでいました。その理由は以下の通りです。
- 給与面でのメリットが大きい(特に未経験からのスタートで年収アップを実現)
- 業務量が日勤より少なく、資格の学習時間を確保しやすい(会社が資格取得を奨励するような環境の場合)
- 夜間のトラブル対応を経験することで、短期間で幅広いスキルを習得できる
実際、夜勤帯は業務の合間に勉強する時間が取れたため、CCNA、LPIC、.com Master ADVANCEなどの資格を取得することができた、とのこと。更に日中の時間を使って資格学習に充てることで、2年間で5つの資格を取得し、キャリアアップにつなげました。
また、夜勤ではシステム障害が発生した際に一次対応する機会が多いため、実践的なトラブルシューティングスキルが身につきます。これは日勤では得られない貴重な経験となりそうです。
独身時代の夜勤は、自己投資の時間を確保しやすく、キャリアの基盤を築くのに非常に有効な選択肢といえるでしょう。
結婚・妊娠・子育てとの両立は可能か
ライフステージが変わり、結婚や妊娠、出産を経験すると、働き方の見直しが必要になります。夜勤と育児の両立は、環境によって大きく左右されます。
私の同僚の例を挙げると、結婚後も夜勤を続けていましたが、妊娠がわかった時点で日勤へ移行しました。これは会社の理解もあり、スムーズに異動できたケースです。また、別の先輩は出産後、完全在宅勤務のインフラエンジニアとして復職し、夜間オンコールのみ担当するという形で両立を図っていました。
子育てとの両立のポイントは以下の通りです。
- 職場の制度整備(在宅勤務、時短勤務、シフト選択制など)
- パートナーの協力体制(家事・育児の分担)
- 保育施設の選択(夜間保育の有無、病児保育など)
- 緊急時のバックアップ体制(親族の協力など)
特に育休明けの働き方としては、以下のようなパターンが多く見られます。
- 完全日勤への移行
- 週2-3日の夜勤+在宅勤務の組み合わせ
- オンコール対応のみ(リモートで障害対応)
- 短時間夜勤(例:22時〜翌2時など)
会社によっては、育児中の女性エンジニア向けに柔軟な勤務形態を用意しているところも増えています。転職や就職の際には、こうした制度の有無も重要な判断材料となるでしょう。
40代・50代以降の働き方と転職事例
年齢を重ねるにつれて、体力的な面から夜勤の負担は大きくなります。40代、50代になると、多くの女性インフラエンジニアは夜勤から別の働き方へシフトしていきます。
- 管理職への昇進(運用チームのマネージャーなど)
- 技術アドバイザーとしての役割(若手育成、技術コンサルティング)
- 日勤・在宅勤務へのシフト(設計・構築業務などにシフト)
- フリーランスとしての独立(培った経験を活かして柔軟な働き方)
実際に50代でインフラエンジニアとして活躍している女性の例では、夜勤経験を活かして若手の教育係となり、マニュアル作成やナレッジ共有の中心的役割を担っていました。長年の経験から培われた知識は非常に貴重であり、年齢を重ねても活躍の場は広がります。
また、40代で夜勤から日勤へシフトし、その後フリーランスとして独立したケースもあります。夜勤で培った緊急対応力や幅広い知識を評価され、コンサルタントとして高単価で仕事を獲得しています。
年齢に合わせた働き方の選択肢は多様であり、夜勤での経験は必ずキャリアの糧となります。体力面での変化に合わせて、知識やスキルを活かせる働き方を柔軟に考えることが大切です。

インフラエンジニアに必要なスキルと資格(女性未経験でも可)
インフラエンジニアとしてのキャリアを築くには、基礎となるスキルと資格が重要です。特に未経験からスタートする場合、何から始めればいいのか迷うことも多いでしょう。ここでは、実際に必要とされるスキルと資格を紹介します。
キャリアの土台となる主要資格
まず押さえておきたい資格は以下の3つです。
1. CCNA(Cisco認定ネットワークアソシエイト) ネットワーク技術の基礎を証明する資格。インフラエンジニアの登竜門的存在で、多くの求人で「CCNA所持者歓迎」と明記されています。ネットワークの基礎概念、ルーティング、スイッチングなどの知識が問われます。
2. LPIC/LinuC(Linux技術者認定) Linuxサーバーの運用・管理能力を証明する資格。レベル1は基本的なコマンド操作や設定、レベル2になるとサーバー構築やセキュリティ管理も含まれます。LPICはグローバル版、LinuCは日本版と考えると良いでしょう。
3. 基本情報技術者 IT全般の基礎知識を問う国家資格。インフラだけでなく、アプリケーション開発やデータベースなど幅広い分野をカバーしています。多くの企業で最低限の資格として求められることが多いです。
私の経験では、未経験からの転職時、LPICレベル1を取得していたことで、面接の通過率が格段に上がりました。特にLPICやCCNAは、未経験の方でも「本気度」を示す資格として、採用担当者から評価されることが多いです。
現場で実際に求められるスキル
資格だけでなく、実務で求められるスキルも押さえておく必要があります。
1. シェル・コマンド操作 Linux/Unixのコマンドを使いこなす能力は必須です。特に「grep」「sed」「awk」などのテキスト処理コマンドや、「bash/shellスクリプト」の基本は押さえておきましょう。
関連👉【Linux】よく使う重要コマンド【30選】【管理者必見】例題付き!
2. 監視ツールの操作 Zabbix、Nagios、Prometheusなどの監視ツールの基本操作。アラートの確認方法、閾値の設定、レポート出力など、運用に必要な操作を理解していることが求められます。
3. 報連相と緊急時の対応能力 技術的なスキル以外に、コミュニケーション能力も重要です。特に夜勤では、問題発生時の報告・連絡・相談(報連相)が適切にできるかどうかが問われます。マニュアルに書かれていない状況でも、冷静に対応できる判断力も求められます。
これらのスキルは、実務経験を通じて身につけていくものが多いですが、事前に学習しておくことで、現場でのスタートがスムーズになります。一例として、転職前に自宅にLinuxサーバーを構築し、実際にコマンド操作やシェルスクリプトを書くことで良い練習になるでしょう。
未経験からの学習ロードマップ
未経験から女性インフラエンジニアを目指す場合、以下のようなステップでスキルアップしていくことをおすすめします。
STEP1: 基礎知識の習得(2〜3ヶ月)
- 基本情報技術者の勉強を通じてIT全般の知識を身につける
- Linuxの基本操作を学ぶ(UdemyやYouTubeの無料講座)
- ネットワークの基礎概念を理解する(CCNA対策本で学習)
STEP2: 資格取得(3〜6ヶ月)
- LPIC/LinuCレベル1の取得
- CCNAの取得
- 可能であれば基本情報技術者試験の受験
STEP3: 実践スキルの習得(2〜3ヶ月)
- 自宅LAB環境の構築(仮想環境でLinuxサーバー構築)
- GitHubで簡単なシェルスクリプトを公開
- AWS/Azureなどのクラウド環境に触れる
STEP4: 就職・転職活動(1〜3ヶ月)
- IT系エージェントへの登録(レバテックキャリア、マイナビITエージェントなど)
- ポートフォリオの作成(自分のスキルや学習履歴をまとめたもの)
- 未経験OKのインフラ運用案件への応募
学習方法としては、以下のような選択肢があります。
- 独学: UdemyやYouTube、技術書を活用した自己学習
- 無料ITスクール: TechAcademyの無料講座や、プログラミングスクールの無料体験など
- 職業訓練校: ハローワーク経由でのIT系職業訓練(3〜6ヶ月程度)
- 短期アルバイト・インターン: 未経験OKのヘルプデスクやキッティング業務などで基礎経験を積む
あるインフラエンジニアの事例ですが、独学で資格を取得した後、SES企業の未経験者向け研修プログラムに参加し、その後夜勤インフラエンジニアとして配属されました。SES企業は未経験者の受け入れに積極的なところが多く、女性のインフラエンジニアも増えています。
重要なのは、資格とポートフォリオの組み合わせです。資格だけでなく、実際に動くものを作った経験(例:自宅サーバーの構築記録など)があると、面接での印象が格段に良くなります。

インフラエンジニアについてなんとなくわかった…!
だけど、まだ具体的な仕事のイメージがわかないなぁ…。

そんなあなたのために!
具体的な一日の流れをご紹介…!
【夜勤の日】インフラエンジニアの実務内容と1日の流れ
夜勤インフラエンジニアの具体的な業務内容と、実際の1日の流れを見ていきましょう。これから夜勤を始める方にとって、実際の業務イメージを持つことは非常に重要です。
夜勤の具体的な業務内容
夜勤対応のインフラエンジニアの主な業務は以下の3つに分類されます。
1. 監視業務(アラート対応・ログ確認) システム監視ツール(Zabbix、Nagios、Prometheusなど)を使って、サーバーやネットワーク機器の状態を常に監視します。アラートが発生した場合は、その原因を調査し、必要に応じて一次対応を行います。また、定期的にログをチェックし、異常がないかを確認します。
例えば、「ディスク使用率80%超過」のアラートが上がった場合、不要ファイルの削除やログローテーションの確認など、定型的な対応を行います。また、アプリケーションエラーログを監視し、異常なパターンがないか分析することも重要な業務です。
2. 障害時の一次対応 システム障害が発生した場合、マニュアルに沿って一次対応を行います。例えば、サーバーがダウンした場合は再起動を試みたり、ネットワーク障害の場合は経路確認やケーブル確認などの基本的なトラブルシューティングを行います。
一次対応で解決しない場合は、エスカレーションフローに従って上長や専門チームに連絡します。大規模な障害の場合は、深夜でも開発チームやベテランのエンジニアを呼び出すことがあります。
3. 定常業務(日報・引き継ぎ) 定期的に実行する定型業務もあります。バックアップの実行と結果確認、バッチ処理の監視、セキュリティパッチの適用など、システムの定期メンテナンス作業を行います。
また、勤務終了時には日報を作成し、発生したアラートや対応内容、引き継ぎ事項などを記録します。日勤帯のチームにスムーズに引き継ぐために、重要な情報を漏れなく記録することが求められます。

特に稼働中システムにおけるバージョンアップ作業は、なるべく顧客に影響が少ない深夜帯に行われることが多く
精神的な負荷が大きいため、最も大変な作業の一つです。
夜勤1日のスケジュール例(23時〜翌8時など)
実際の夜勤のスケジュール例を示します。これは23時〜翌8時の夜勤の一例です。
22:30〜23:00: 出社・準備
- 日勤帯からの引き継ぎ資料確認
- 監視システムの状態チェック
- 当日の作業予定の確認
23:00〜23:30: 日勤帯からの引き継ぎ
- 発生中の問題や懸念事項の共有
- 特殊対応が必要な事項の確認
- 質問や疑問点の解消
23:30〜1:00: 定常チェック業務
- 全システムの監視画面確認
- バックアップ処理の結果確認
- バッチ処理の実行状況確認
1:00〜3:00: 仮眠タイム(交代制)
- チームメンバーと交代で仮眠
- 緊急時はコールで起こされる仕組み
3:00〜5:00: 深夜帯の監視強化
- システムリソースの定期チェック
- セキュリティログの確認
- 異常パターンの有無確認
5:00〜6:30: 早朝バッチ監視
- 早朝に実行される重要バッチの監視
- エラー発生時の対応
- 処理完了の確認
6:30〜7:30: 日報作成
- 夜間の対応内容のまとめ
- 発生したアラート・対応結果の記録
- 日勤帯への引き継ぎ事項の整理
7:30〜8:00: 日勤帯へ引き継ぎ
- 発生した問題と対応状況の説明
- 継続対応が必要な事項の共有
- 質問対応
夜勤では、このようなスケジュールで業務が進行しますが、実際には突発的なトラブル対応が入ることもあります。深夜2時にサーバーダウンのアラートが発生し、復旧作業に2時間かかったという苦労話も。そのため、柔軟に対応できる心構えが必要です。
仮眠時間の確保は夜勤を乗り切るための重要なポイントです。最近では、2〜3時間程度の仮眠が認められてる職場もあり、取得方法は職場によって異なります。指定された仮眠室がある場合もあれば、デスクで仮眠を取る場合もあります。ある職場では専用の仮眠ベッドが用意されており、交代制で利用しているそうです。
また、深夜帯(2時〜5時)は特に注意力が低下しやすい時間帯です。この時間帯は定期的に立ち上がって軽いストレッチをしたり、冷たい水を飲んだりすることで眠気対策をするのもおすすめです。一人勤務の場合は特に、眠気との戦いが大きな課題となります。
日勤との違いと業務負荷
夜勤と日勤では、業務内容や負荷に大きな違いがあります。主な違いは以下の通りです:
1. 突発対応の頻度 日勤帯はユーザーからの問い合わせやシステム変更作業が多く、常に何かしらの対応に追われることが多いです。一方、夜勤は基本的に監視業務がメインとなり、突発的なトラブルがなければ比較的落ち着いて業務を行えます。ただし、いざトラブルが発生すると、少人数もしくは一人で対応する必要があるため、プレッシャーは大きくなります。
2. 業務の自由度 日勤は複数人でチームを組んで作業することが多く、柔軟な対応が求められます。夜勤は基本的にマニュアルやチェックリストに沿った定型業務が中心で、手順が明確に決まっていることが多いです。そのため、未経験者にとっては夜勤の方が取り組みやすい面もあります。
3. コミュニケーション量 日勤では様々な部署やユーザーとのコミュニケーションが発生しますが、夜勤はコミュニケーション量が圧倒的に少なくなります。これは気楽な反面、孤独感を感じる原因にもなります。特に一人勤務の場合、8〜9時間誰とも会話しない状況が続くこともあります。
4. 精神的負荷 夜勤特有の精神的負荷として、「何か問題が起きたらどうしよう」という不安感があります。特に大規模システムの場合、自分の判断で対応できないトラブルが発生すると、上司や専門チームを深夜に呼び出すことになるため、精神的なプレッシャーを感じることがあります。
日勤は「忙しいが充実感がある」、夜勤は「比較的落ち着いているが孤独と眠気との戦い」という印象です。どちらが合うかは個人の性格や生活スタイルによって異なります。
夜勤で特に大変だったのは、日中との連携不足によるストレスです。例えば、日勤帯で決まった変更事項が夜勤に正確に伝わっていない、夜勤で報告した問題が翌日以降フォローアップされていないなど、情報共有の齟齬が生じることも有り得ます。この問題を解消するためには、引き継ぎ資料の充実やチャットツールでの情報共有を徹底することが重要です。
SESや常駐案件で夜勤する際の注意点
インフラエンジニアとして夜勤を行う場合、多くの方がSES(システムエンジニアリングサービス)企業や派遣会社から客先常駐する形態で働くことになります。この働き方には特有の注意点があるので、事前に理解しておくことが重要です。
雇用形態・契約内容の落とし穴
SESや派遣で夜勤を行う場合、以下の点に特に注意が必要です:
1. 契約条件の曖昧さ 夜勤の勤務時間や休憩時間、仮眠可否などが契約書に明記されていないケースがあります。「夜勤」と言っても、22時〜翌7時の場合もあれば、17時〜翌2時といった変則的な時間の場合もあります。契約前に必ず勤務時間の詳細を確認しましょう。
私の知人は、「夜勤」という説明だけで入社したところ、実際は「準夜勤(17時〜翌2時)」と「深夜勤(22時〜翌7時)」が1週間ごとに入れ替わるシフトで、体調を崩してしまったケースがありました。事前に勤務形態を詳細に確認することが重要です。
2. 深夜手当の計算方法 深夜手当(22時〜翌5時の割増賃金)の計算方法は企業によって異なります。法律上は25%以上の割増が必要ですが、基本給に深夜手当を含む「みなし深夜手当」として支給されるケースもあります。この場合、見かけの時給は高くても、実質的な深夜手当が少ないということがあり得ます。
給与明細の内訳を確認し、深夜手当が適切に支払われているか確認することが大切です。
3. 仮眠の可否と環境 夜勤で重要なのが仮眠の取得可否です。契約上は仮眠が認められていても、実際の現場では「忙しくて取れない」ということもあります。また、仮眠室の環境も重要なポイントです。簡易ベッドが用意されているか、男女別の仮眠室があるかなど、事前に確認しておくと安心です。
女性エンジニアとして特に気になるのが、仮眠室の環境です。男女共用の仮眠室しかない現場もあり、女性にとって落ち着いて休めない環境というケースも少なくありません。面接時に仮眠環境についても質問しておくことをおすすめします。
勤務先による働き方の違い
SESや派遣の場合、配属先によって働き方が大きく異なります。主な違いは以下の通りです。
1. 自社勤務 vs クライアント常駐 自社内の監視センターで勤務する場合と、クライアント先に常駐する場合では環境が大きく異なります。自社内であれば複数のプロジェクトを担当することも多く、様々な経験を積める反面、業務量が多くなりがちです。一方、常駐の場合は特定のシステムに特化した知識が身につきますが、範囲が限定的になる傾向があります。
私の知り合いのインフラエンジニアは最初の2年間は自社の監視センターで複数のクライアントシステムを担当し、その後特定の金融系クライアントに常駐しました。自社勤務時代は幅広い知識が身についた一方、常駐後はより専門的なスキルを磨くことができました。どちらが良いかは、キャリア目標によって異なります。
2. チームで働けるか単独作業か 夜勤は1人で担当する「一人勤務」と、複数人で担当する「チーム勤務」があります。一人勤務は精神的な負担が大きい反面、自分のペースで働けるメリットがあります。チーム勤務は心強い反面、チームワークが求められ、人間関係の構築が必要です。
女性エンジニアとしては、特に一人勤務の場合、精神面の不安もあるかもしれません。最初はチーム勤務(2〜3人体制)から始め、経験を積んだ後に一人勤務にシフトするというパターンであれば安心です。初めての夜勤であれば、可能な限りチーム体制の環境を選ぶことをおすすめします。
3. 運用設計に関わるチャンスの有無 単純な監視業務だけでなく、運用設計や改善提案に関われるかどうかもキャリア形成において重要です。一部の現場では「指示された作業だけを行う」役割に限定されることもありますが、中には積極的に改善提案を取り入れる環境もあります。
キャリアアップを考えるなら、単なる「監視オペレーター」ではなく、「運用エンジニア」として関われる環境を選ぶことが重要です。面接時に「改善提案は受け入れられる環境か」「運用設計にも携われる可能性があるか」を質問してみるとよいでしょう。
キャリア形成を考慮した案件選び
長期的なキャリア形成を考えると、夜勤案件の選び方も重要になります。以下のポイントを意識して案件を選びましょう。
1. 夜勤でも設計や構築に携われるか 単純な監視業務だけでなく、システム改善や設計・構築フェーズにも関われる案件が理想的です。例えば、深夜帯のメンテナンス作業で設定変更やアップデート作業を担当できる案件は、スキルアップの観点で価値があります。
最初は単純な監視業務でも、数年後にシステム改善プロジェクトのメンバーとして声をかけてもらえるようになる可能性が高いです。日勤メンバーとの連携を密にし、積極的に提案することで、単なる監視業務以上の経験を積むこともできます。
2. 将来的に社内SEやフリーランスへ繋がるか 夜勤の経験を将来どう活かすかも考慮に入れましょう。特定業界のシステム(金融、製造、医療など)の知識を深められる案件は、その業界の社内SEへの転職に有利になります。また、特定の技術(AWS、Azure、セキュリティなど)に特化した案件は、将来フリーランスとして独立する際の強みになります。
例えば、金融系システムの夜勤経験は、銀行や証券会社の社内SEへの転職に有利に働きます。また、クラウド環境の運用経験は、将来的にクラウドコンサルタントとしての道も開けます。
3. 成長できる環境かを見極める視点 案件を選ぶ際に、以下のような点をチェックすると良いでしょう。
- トレーニング・研修制度の有無
- 社内勉強会や技術共有の仕組み
- 資格取得支援制度の有無
- 先輩エンジニアからの指導体制
- 日勤帯との連携や交流機会の有無
特に重視すべきなのは「先輩女性エンジニアの存在」です。実際に同じ環境で働いている先輩女性の話を聞くことで、現実的なキャリアイメージを持つことができます。可能であれば、面接時に「女性エンジニアの在籍状況」や「女性の夜勤事例」について質問してみることをおすすめします。
夜勤で働く女性エンジニアたちのリアル体験談
実際に夜勤で働く女性インフラエンジニアたちの体験談を紹介します。それぞれのライフステージで直面する課題や工夫を知ることで、自分自身のキャリアプランを考える参考になるでしょう。
未経験から夜勤インフラエンジニアになった20代女性
Aさん(28歳・エンジニア歴2年)の場合
元々は一般事務職として働いていたAさんは、IT業界への転職を決意。未経験から独学でCCNAを取得し、SES企業に転職しました。最初は日勤のヘルプデスク業務からスタートしましたが、半年後に夜勤インフラ監視チームへ異動しました。
「最初の夜勤は本当に大変でした。前職は9時〜17時の事務職だったので、生活リズムが180度変わりました。最初の1ヶ月は体がついていかず、休日は寝てばかりでした。特に辛かったのは、夜勤明けの日に誘われた飲み会や予定をほとんど断ることになったこと。友人関係が希薄になる感覚がありました」
しかし、徐々に体が慣れてくると、夜勤ならではのメリットも感じるようになったといいます。
「夜勤の大きなメリットは、平日の昼間に自由な時間が持てること。銀行や病院、役所など、平日しか行けない場所にスムーズに行けるのは大きいです。また、夜勤手当で収入が増えたことで、より良い環境で一人暮らしができるようになりました」
キャリア面では、日勤よりも自己学習の時間が取れたことが大きかったと言います。
「夜勤は監視業務の合間に勉強する時間が取れました。その時間を使って、CCNAに続きAWS認定資格も取得。日中だとそこまでまとまった勉強時間は取れなかったと思います。また、深夜のトラブル対応を経験することで、実践的なスキルも身につきました」
Aさんのアドバイス:「未経験から夜勤を始める場合は、まず短期間(3ヶ月程度)を目標に挑戦してみることをおすすめします。自分に合うかどうかは実際に経験してみないとわかりません。また、事前にCCNAなどの基礎資格を取得しておくと、業務に入りやすくなります」
30代で結婚・子育てと両立する現役エンジニア
Bさん(34歳・エンジニア歴8年)の場合
大学でIT系の学部を卒業し、新卒でSIer企業に入社したBさん。入社4年目から夜勤インフラ担当として働き始め、30歳で結婚。32歳で出産し、現在は2歳の子どもを育てながら週3回の夜勤勤務を続けています。
「結婚当初は夜勤を問題なく続けられましたが、妊娠がわかった時点で日勤に異動しました。出産後は完全在宅の業務に切り替え、子どもが1歳になったタイミングで週3回の夜勤に復帰しました」
育児と夜勤の両立は、パートナーと保育園の協力が鍵だったと言います。
「夫は在宅勤務が可能な職場で、夜勤の日は夫が保育園の送迎と夕食を担当してくれます。私は夜勤前に仮眠を取り、夜勤明けは保育園のお迎えまで睡眠時間を確保しています。週3回の夜勤なので、残りの4日は通常の生活リズムで過ごせるのもバランスが取りやすいポイントです」
夜勤と育児のスケジュール管理については、細かく計画を立てることが重要だと言います。
「例えば、夜勤の前日は夫が子どもと公園に行き、私は十分な睡眠を取ります。夜勤明けの日は、保育園からの緊急連絡は夫が対応する約束にしています。また、実家の母に月に1〜2回来てもらい、家事のサポートをしてもらっています」
キャリア面では、夜勤経験が専門性の向上につながったと感じています。
「夜間のトラブル対応は自分で判断して行動する必要があるため、技術力だけでなく、判断力や責任感も養われました。これらの経験は、将来管理職を目指す上でも貴重だと思います。また、夜勤チームのリーダーを任されたことで、リーダーシップを発揮する機会も得られました」
Bさんのアドバイス:「育児と夜勤を両立するには、パートナーの理解と協力が絶対条件です。また、無理なく続けられるシフト(週2〜3回など)を選ぶことも重要。職場の理解を得て、子どもの体調不良時などに柔軟に対応できる環境を整えておくことが大切です」
夜勤経験を経てフリーランスへ転身した40代女性
Cさん(45歳・エンジニア歴15年)の場合
30代前半でIT業界に転職し、7年間の夜勤インフラエンジニア経験を経て、現在はフリーランスコンサルタントとして活躍するCさん。夜勤経験が現在のキャリアにどう影響したかを語ってくれました。
「30代前半で未経験からIT業界に飛び込み、最初の2年はヘルプデスクで経験を積みました。その後、給与アップを目指して夜勤インフラエンジニアに転向。金融系システムの監視業務から始まり、徐々に設計・構築フェーズにも関わるようになりました」
夜勤で培ったスキルが、現在のフリーランス活動に大きく役立っていると言います。
「夜勤では、緊急時に自分で判断して行動する力が養われます。また、様々なトラブルに対応することで、広範囲の技術知識も身につきました。特に金融系システムの専門知識は、現在のコンサルティング業務でも強みになっています」
40代になって夜勤から日勤へシフトした理由は、体力面の変化だったと言います。
「40歳を過ぎると、夜勤後の回復に時間がかかるようになりました。以前は夜勤明けの日に少し睡眠を取れば回復していましたが、年齢を重ねるにつれて1日では回復しきれなくなりました。そこで日勤の設計・構築業務にシフトし、その後フリーランスとして独立しました」
フリーランスとして営業せずに案件を獲得できる理由は、夜勤時代の人脈だと言います。
「夜勤時代に対応した緊急トラブルで、多くのプロジェクトマネージャーや開発チームと関わりました。その際の対応が評価され、『あの時助けてくれたエンジニア』として覚えてもらえていたようです。独立後も、元クライアントからの紹介で案件をいただくことが多いです」
Cさんのアドバイス:「夜勤は若いうちの『一時的な選択』として考えるのがおすすめです。給与面でのメリットを活かしつつ、その時間を使ってスキルアップし、将来のキャリアに繋げることが大切。また、夜勤だからこそできる人脈形成(緊急時に頼られる存在になること)も意識すると、将来の選択肢が広がります」
よくある質問と誤解(FAQ)
インフラエンジニアの夜勤に関して、よくある質問や誤解について回答します。特に女性目線での懸念点にフォーカスしてお答えします。
Q. 女性に夜勤は本当にきついの?
A. 個人差はありますが、体力面では確かに女性にとって負担が大きい傾向があります。特に生理周期でホルモンバランスが変化する時期は、夜勤による体への影響がより大きく感じることがあります。
しかし、「女性だから夜勤に向いていない」というわけではありません。適切な休息と生活習慣の管理、職場環境の整備次第で、多くの女性が夜勤を問題なくこなしています。短期間(2〜3年程度)であれば、キャリアアップの手段として有効な選択肢の一つです。
ただし、長期間の夜勤は男女問わず健康リスクが高まるため、5年以上続ける場合は定期的な健康チェックを受けることをおすすめします。
Q. 仮眠は必ず取れる?起きてなきゃダメ?
A. 仮眠の取得可否は職場によって大きく異なります。最近では2〜3時間程度の仮眠が認められている職場があり、中には以下のようなパターンもあります。
- 正式に仮眠が認められ、仮眠室が用意されている
- 公式には認められていないが、暗黙の了解で取得できる
- 常に監視業務を行う必要があり、仮眠が不可
仮眠の取り方も様々で、交代制で取る場合もあれば、アラートがない時間帯に適宜取る場合もあります。また、仮眠中でもアラート発生時には即座に対応する必要がある場合がほとんどです。
女性にとって重要なのは、仮眠環境の確認です。「女性用の仮眠室がある」「個室で休める」などの環境があると安心です。面接時に仮眠についての条件を具体的に確認しておくことをおすすめします。
Q. 夜勤経験はキャリアに不利?
A. むしろ逆です。インフラエンジニアとしてのキャリアにおいて、夜勤経験はプラスに評価されることが多いです。その理由は以下の通りです。
- 緊急時の対応力が身につく(判断力・実行力)
- 幅広いトラブルシューティング経験が積める
- 「夜勤をこなせる」という実績自体が評価される
特に、キャリアの初期段階で夜勤を経験することで、短期間で様々なケースに対応するスキルが身につきます。日勤だけでは経験できない障害対応なども経験できるため、技術的な引き出しが増えるというメリットがあります。
私の周囲でも、夜勤経験者は次のステップ(設計・構築フェーズや上流工程)へのキャリアアップがスムーズなケースが多いです。ただし、長期間(5年以上)夜勤のみを続けると、設計や開発などの経験が不足するリスクもあるため、バランスが重要です。
Q. 文系・未経験でもなれる?
A. はい、十分可能です。むしろインフラエンジニアは、プログラミングエンジニアよりも文系出身者が活躍しやすい分野とも言えます。なぜなら、論理的思考力とコミュニケーション能力があれば、技術は後から身につけられるからです。
実際に私の周囲でも、元事務職、販売職から転職した女性のインフラエンジニアが何人も活躍しています。大切なのは以下のポイントです。
- 基礎的な資格(CCNA、LPIC/LinuCレベル1など)の取得
- 自宅LAB環境での実践経験(仮想環境でサーバー構築など)
- 未経験OKの求人への積極的なアプローチ
特に女性の場合、「コミュニケーション能力が高い」「ドキュメント作成が丁寧」といった強みを評価されるケースも多いです。未経験からでも、適切な学習と資格取得によって、十分にインフラエンジニアとしてのキャリアをスタートさせることができます。
Q. どんな求人サイトやエージェントが良い?
A. 女性インフラエンジニア、特に夜勤案件を探す場合におすすめの求人サイトやエージェントは以下の通りです。
- レバテックキャリア:IT専門のエージェントで、未経験者向けの案件も多数。女性エンジニア向けのサポートも充実しています。
- マイナビITエージェント:未経験からIT業界を目指す女性向けのサポートが手厚いです。研修制度がある企業も多く紹介してくれます。
- Geekly(ギークリー):IT・WEB・ゲーム業界特化型で、夜勤含めたインフラ案件が豊富。女性エンジニアのキャリア支援にも力を入れています。
- リクルートエージェント IT:大手ならではの豊富な求人数と、女性活躍を推進する企業の求人が多いのが特徴です。
エージェントを利用する際は、以下の点を明確に伝えることがポイントです。
- 夜勤業務に興味がある旨
- 希望する勤務時間帯(固定夜勤か交代制か)
- 女性エンジニアとしてのキャリア希望(将来的に日勤や在宅へ移行したいなど)
これらを事前に整理しておくことで、ミスマッチを防ぎ、希望に近い職場を見つけやすくなります。
インフラエンジニアを目指す女性におすすめの書籍5選
技術書選びに悩んでいませんか?キャリアアップのための最適な知識を得るために、特におすすめの書籍をご紹介します。これらの本はスキルアップだけでなく、あなたのキャリアの可能性を広げるきっかけになるでしょう。
1. 『インフラエンジニアの教科書』
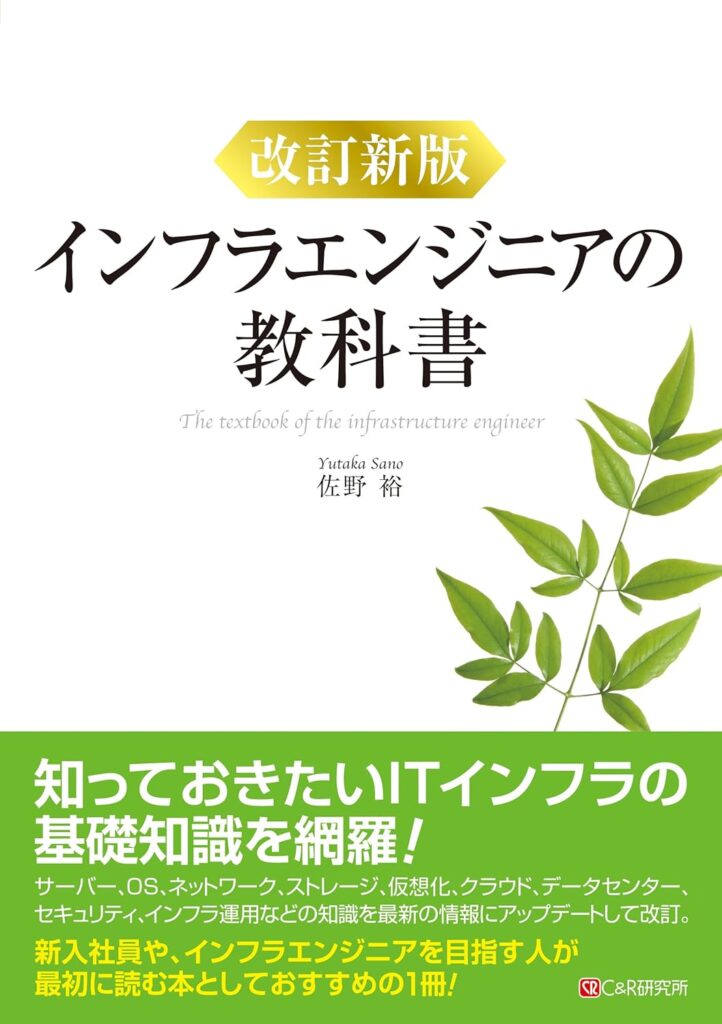
なぜこの本が必読なのか
『インフラエンジニアの教科書』は、インフラ領域の基礎から実践まで幅広くカバーした、まさに「教科書」と呼ぶにふさわしい一冊です。特に未経験からの転職を目指す方にも理解しやすい構成になっています。
サーバー、ネットワーク、セキュリティの基本概念から、クラウドサービスの活用方法まで、体系的に学ぶことができます。特に女性読者からは「専門用語の解説が丁寧で、IT業界未経験でも理解できた」という声が多く寄せられています。実務で使える知識が詰まったこの本を読破することで、面接での専門的な質問にも自信を持って答えられるようになります。(Amazonでチェック👉✨)
2. 『ゼロからわかるAWS入門』
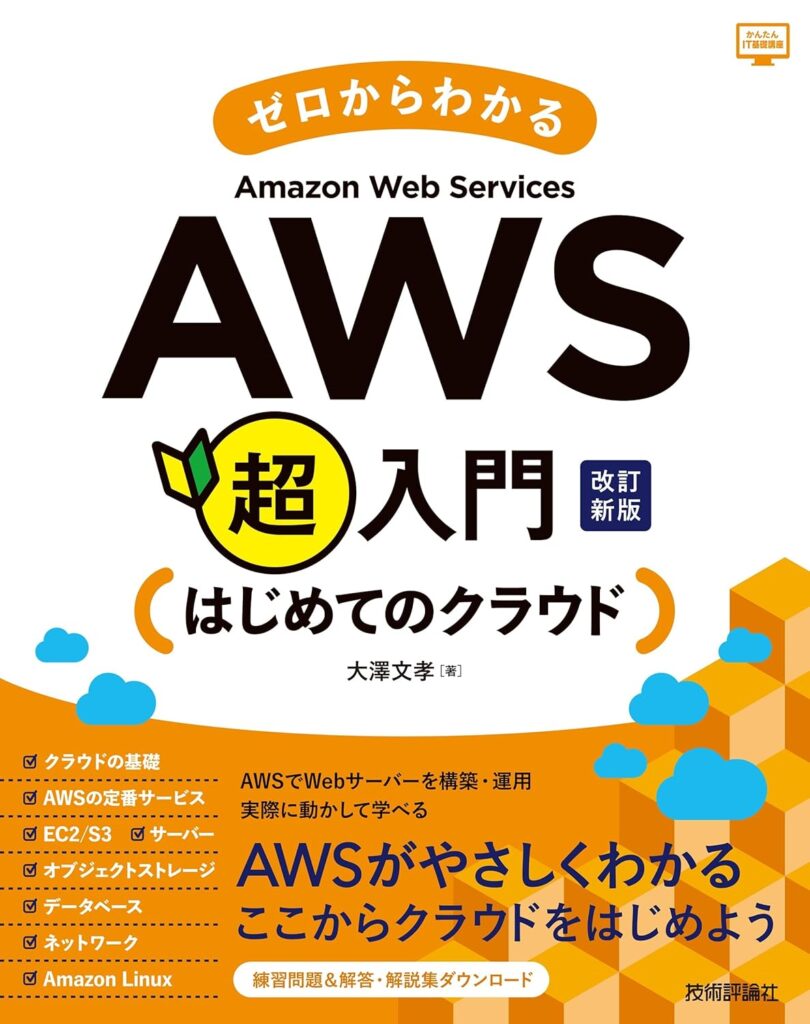
クラウドスキルで差をつける
現代のインフラエンジニアにとって、クラウドサービスの知識は必須です。特にAWSは業界標準として多くの企業で採用されています。『ゼロからわかるAWS入門』は、AWS初心者のために書かれた分かりやすいガイドブックです。
この本の魅力は、ハンズオンで学べる構成になっていること。AWSアカウントの作成から、主要サービス(EC2、S3など)の設定など、手を動かしながら学ぶことができます。著者は多数のエンジニア向けの本を執筆しており、エンジニアコミュニティでも活躍している方なので、ぜひチェックしてみることをおすすめします。この本で基本を押さえておけば、履歴書にAWSのスキルを自信を持って記載できるようになります。(Amazonでチェック👉✨)
3. 『Linux標準教科書』
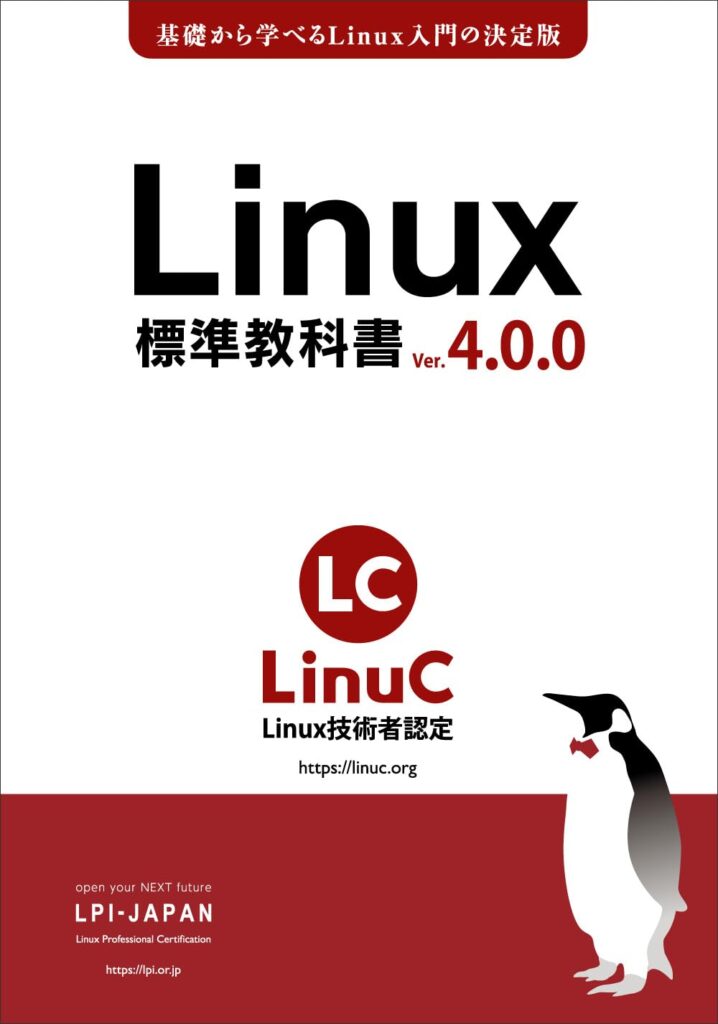
オープンソースの力を味方につける
インフラエンジニアにとって、Linuxの知識は不可欠です。『Linux標準教科書』は、初心者から中級者まで幅広いレベルに対応した実践的な一冊です。
コマンドラインの基本操作からシェルスクリプト、システム管理の方法まで、段階的に学ぶことができます。特に女性エンジニアからは「技術書特有の難解な表現が少なく、挫折せずに最後まで読み切れた」という感想が多いのが特徴です。
この本の学習を通じて得られるLinuxスキルは、どんなインフラ環境でも応用が利き、あなたの市場価値を確実に高めます。実務経験がなくても、この本の内容をマスターしていれば面接官に技術力をアピールできるでしょう。(Amazonでチェック👉✨)
4. 『【改訂5版】図解でよくわかる ネットワークの重要用語解説』
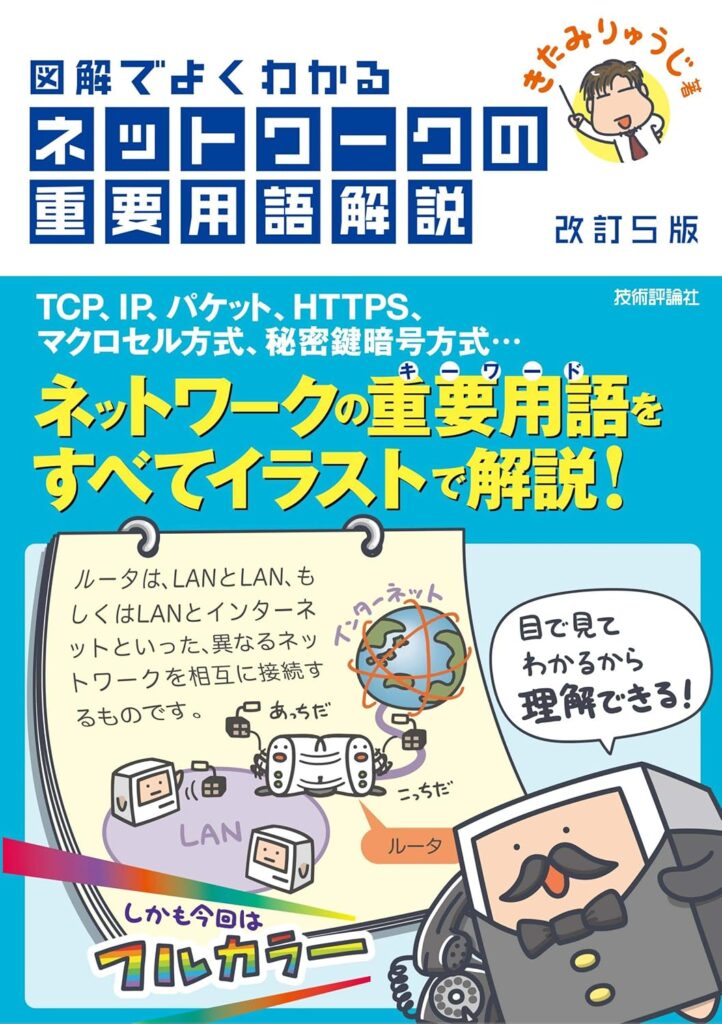
難解なネットワーク用語もスンナリ理解できる
『図解でわかるネットワーク入門』は、複雑に思えるネットワークの概念を視覚的に理解できる工夫が満載です。ルータの基礎から、LANやインターネットまで、豊富な図解で解説されています。
特に女性読者からは「抽象的な概念が図解でスッと理解できた」「技術的な会話に自信が持てるようになった」という声が寄せられています。エンジニア同士のコミュニケーションでもネットワーク用語は頻出するため、この本を読むことで技術的な会話にも自信を持って参加できるようになります。
面接でも「ネットワークの基礎知識がある」と示せることで、即戦力として評価される可能性が高まります。(Amazonでチェック👉✨)
5. 『DevOpsハンドブック』

次世代のインフラエンジニアへのステップアップ
最後に紹介するのは『DevOpsハンドブック』です。この本は従来のインフラ管理の枠を超え、実践的なDevOps文化について学べる一冊です。
自動化、継続的インテグレーション、継続的デリバリーなど、最新のインフラ管理手法について深く理解できます。「何から手を付けていけばいいの?」という疑問に対する具体的な答えが示されており、入門としてもおすすめの書籍です。
この本を読破してDevOpsの知識を身につければ、単なるインフラ管理者ではなく、組織全体の開発プロセスを改善できる戦略的な人材として自分をアピールできるようになりますよ。(Amazonでチェック👉✨)
Udemyで学ぶインフラエンジニアスキル
オンライン学習で実践力を磨く
書籍だけでなく、動画教材で学ぶこともおすすめです。Udemyには、インフラエンジニアに必要なスキルを体系的に学べる講座が多数あります。特に以下の講座は女性エンジニアからも高評価を得ています。
※ 2025.05時点の情報であり、現在は変更されている可能性もあります。詳細はUdemy公式サイトをご確認ください。
- 「【SAA-C03版】これだけでOK! AWS 認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト試験突破講座」 – クラウドインフラの設計・構築スキルを証明できる資格取得を目指す講座です。実際の画面操作を見ながら学べるので、実践的なスキルが身につきます。
- 「はじめてのLinuxサーバー構築運用入門 – Linuxコマンドを基礎から学ぶ」 – 基本コマンドからサーバー構築まで、ハンズオン形式で学べます。特に実務経験がない方でも、この講座を修了すれば実践的なスキルをアピールできます。開発エンジニアの女性にもおすすめ。
- 「ネットワークエンジニアを目指す初心者はここから始めよう!「ゼロから学ぶネットワーク基礎」豊富な図解で徹底解説」 – ネットワークの基本的な概念を学び、IPやEthernetの理解を深めることで、確実な基礎を築くことができるのでおすすめ。標準的な技術に基づいた内容で、初心者が安心して学べるように設計されています。
これらの講座は、書籍で学んだ知識を実践的なスキルに変換するのに最適です。修了証も発行できるため、技術習得の証明として活用できます。
これらの書籍と学習リソースを活用すれば、インフラエンジニアとしてのキャリアの第一歩を力強く踏み出せるはずです。技術力とともに自信も身につけて、IT業界で活躍する女性エンジニアの仲間入りを目指しましょう!
まとめ|女性が夜勤のインフラエンジニアとして働くために大切なこと
インフラエンジニアとして夜勤に従事することは、体力的・生活リズム的には確かにハードルがあります。しかし、正しい準備と理解があれば、夜勤は「自由な時間の確保」や「高収入」といった大きなメリットもあります。
特に女性の場合、ライフステージと両立できる働き方を模索する中で、夜勤という選択肢が視野に入ることもあるでしょう。大切なのは、以下のポイントを押さえることです。
- 夜勤のメリット・デメリットを正しく理解する
- スキルと資格(CCNA・LPICなど)で将来の選択肢を増やす
- キャリアの方向性を持ち、将来的な日勤や在宅勤務も見据えて行動する
夜勤という働き方を通じて、自分に合ったペースでキャリアを築いていくことは十分に可能です。無理なく続けるためには、パートナーや家族の協力、そして何より自分自身の価値観に合った職場選びがカギになります。
あなたの「小さな一歩」が、大きな変化につながりますように。

私でもインフラエンジニアになれそうな気がしてきた…!
キャリアアップにご興味のある方は以下の記事も参考にしてみてください!
インフラエンジニアになりたい女性へ【夜勤でも大丈夫】|参考リンク
- 女性インフラエンジニアにおすすめ①:改訂新版 インフラエンジニアの教科書
- 女性インフラエンジニアにおすすめ②:ゼロからわかるAmazon Web Services超入門 はじめてのクラウド 改訂新版 (かんたんIT基礎講座)
- 女性インフラエンジニアにおすすめ③:Linux標準教科書 Ver.4.0.0: LinuC(リナック)学習にも役立つ (LPI-Japan標準教科書シリーズ)
- 女性インフラエンジニアにおすすめ④:【改訂5版】図解でよくわかる ネットワークの重要用語解説
- 女性インフラエンジニアにおすすめ⑤:The DevOps ハンドブック 理論・原則・実践のすべて